断捨離が進まない……。
モノは減ったはずなのに、なぜか満足できない……。
そんな“もやもや”の原因は、断捨離の「目標」があやふやだからかもしれません。
私自身、たくさんのモノを手放したあと、
「これで良かったのかな?」と、なんとなく満たされない感覚が残っていました。
もしあなたも、
「どんな暮らしを目指せばいいのかわからない」
という状態なら、私がいま目指している姿を、1つの参考にしてみてください。
それが──
「自分を本当に幸せにしてくれるモノだけに囲まれた、自分らしいミニマリスト」
この記事では、この“目標のカタチ”についてお話しします。
きっと、ただ捨てるだけだった断捨離が、
もっと前向きで、もっと満足度の高いものに変わるはずです。
断捨離の目標:持っているモノを全て把握する
断捨離の目標を考える前に、そもそも「なぜ私たちはモノを持つのか?」を見つめてみましょう。
モノを持つ理由──それはきっと、
- 生活を便利にするため
- 自信や安心感を得るため
- 愛情や癒しを感じるため
どれも突きつめると、「幸せになるため」にモノを持っている、と言えるのではないでしょうか。
でも──
モノが増えすぎると、かえってストレスや不自由さを感じることもありますよね。
不思議なことに、モノは幸せもくれるけど、持ちすぎると不幸の種にもなる。
このバランスが、とても難しいのです。
では、「ちょうどいいモノの量」ってどれくらい?
この記事での答えは、こうです:
「自分を幸せにしてくれるモノを、ちゃんと把握できている状態」
つまり、
「どこに・何が・いくつあるか」が、自分でわかっている状態
たとえるなら、仲良しメンバーだけで集まる食事会のような、心地よく満たされた暮らし。
これが、この記事で紹介する「断捨離の目標」です。
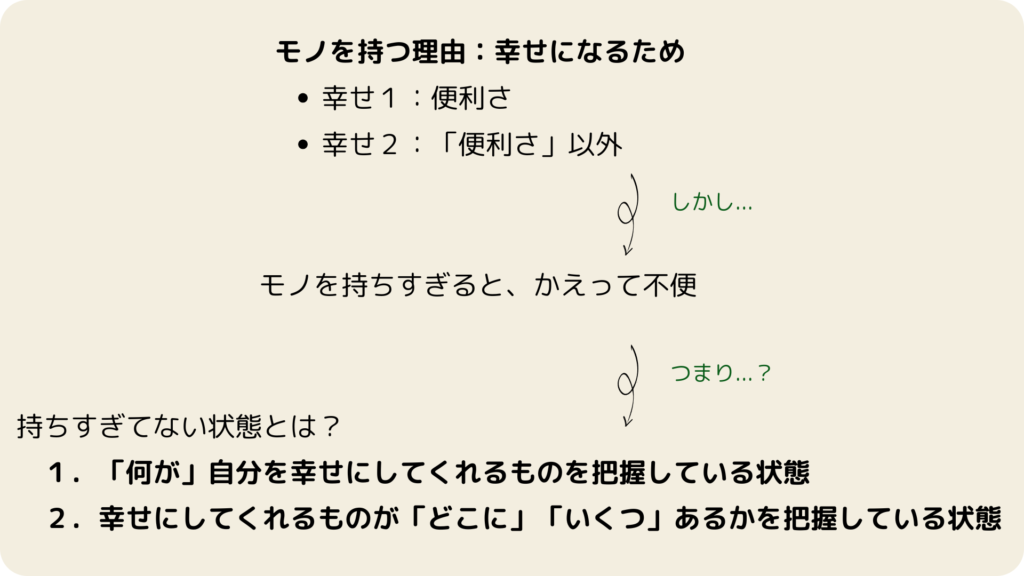
2種類のモノを把握することが断捨離の目標
断捨離の目標は、
「自分を幸せにしてくれるモノだけに囲まれた暮らし」
では、「自分を幸せにしてくれるモノ」とは何でしょうか?
幸せにしてくれるモノとは、次の2種類です。
1.生活に必要なモノ
提供してくれる幸せ:便利さ
2.自分にとって大切なモノ
提供してくれる幸せ:元気、わくわく、高揚感、自己肯定感、愛情、癒し…
まず、断捨離で意識して減らすモノは―――
「1.生活に必要なモノ」です。
1.必要なモノ
必要なものが与えてくれる幸せは、「便利さ」。
ただし、この便利さには、ちょっとした落とし穴があります。
それは──
便利さから得られる幸せ感は、役割が重複すると下がる。
例えば、洗濯機は便利ですが、3台も持っていれば、逆に不便ですよね。
暖を取るのに、空調とヒーターとストーブと、3つも持っていたら、管理が大変です。
便利グッズも持ちすぎていればストレスの原因に。
だから、便利さを提供してくれるモノは、必要最小限にするべきです。
言い換えると、
「自分を幸せにしてくれるモノだけに囲まれた生活」
=「必要なモノを最小限に厳選すること」
2.大切なモノ
自分にとって大切なモノとは感情に直接働きかけてくれる存在。
- 人からもらった手紙:愛情、癒し
- 頑張った証:自信、自己肯定感、自尊心
- 趣味の道具:癒し、元気
「大切なモノ」の判断は、案外むずかしくありません。
「これがあると、今の自分は幸せだな」と感じられるかどうか。
自分の心を豊かにしてくれるものを、無理して減らす必要はありません。
必要なモノを最小限にすることが、大切なモノからもらえる幸せを最大限にします。
断捨離の目標のまとめ
断捨離の目標とは、
「自分を幸せにしてくれるモノだけに囲まれた暮らし」
そのための方針は、次の2つ。
- 必要なモノは最小限
- 大切なモノは最大限
そして、この状態にはもっと具体的にいうと、
「どこに・何が・いくつあるか、自分で把握できている状態」
これが、“自分を幸せにするメンバーだけ”が揃った、理想の暮らしのかたちです。
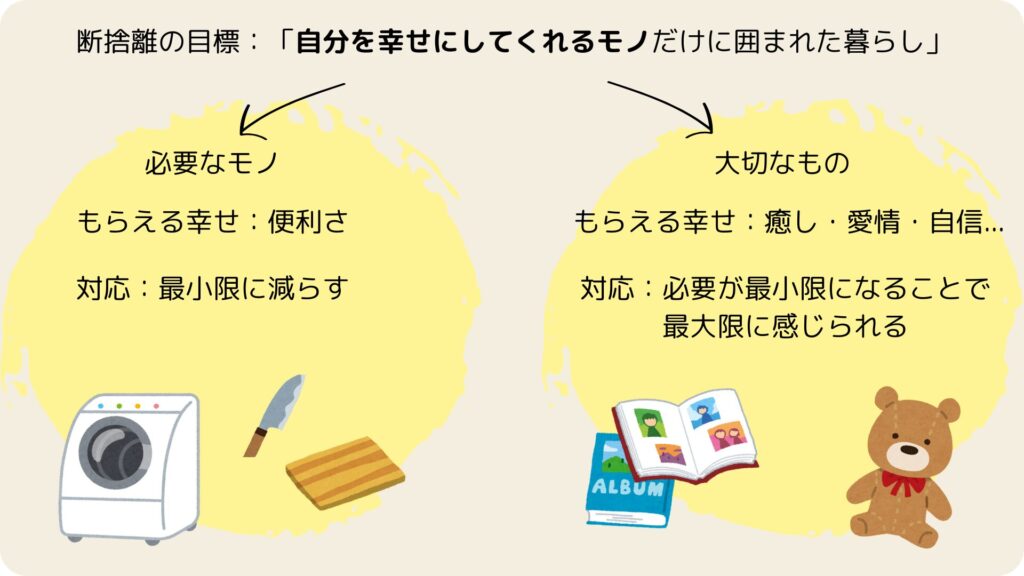
断捨離の目標達成のために必要なのは「考える」
ここまでで、断捨離で目指す状態を明確にしました。
断捨離の目標↓
「自分を本当に幸せにしてくれるモノたち」だけに囲まれた、自分らしいミニマリスト
この状態に近づくには、
自分にとって必要最小限を把握する
ことが欠かせません。
そこで登場するのが、「断捨離ノート」です。
断捨離ノートが必須
必要を最小限にするには、断捨離ノートがとても効果的。
ノートを使うことで、次のようなメリットがあります。
- 今の持ち物を客観的に“見える化”できる(現状把握が正確に)
- 頭の中を整理しながら、本気で考えられる(思考に集中できる)
- 結果:必要最小限を効率よく見極められる
断捨離ノートの書き方
1.持っているものを全て書き出す
2.「必要」「大切」「保留」に分ける
3.「必要」について以下のことについて考える
<代わりになるものは?>
<何のために使うの?>
<どんな幸せをくれるの?>
なぜ、「考えること」が必要なのか?
そもそも、必要最小限を把握するために、なぜ「考えること」が大事なのでしょうか?
理由はシンプルです。
- 必要を最小限にすることは、結構難しい問題だから
- 答えはあなたの中にしかないから
次の章では、この2つの理由について、もう少し詳しくお話しします。
「必要」を最小限にすることは難しい
「必要なモノを最小限にする」と聞くと、
「じゃあ、いらないものを捨てればいいだけ」と思われがち。
でも実際、頭の中で完結するほど簡単な作業ではないんです。
例えば、ハンガーを手放すことを例に考えてみましょう。
仮に、「服の枚数分をのハンガーがあればOK」とした場合でも、
次のように、いくつものことを考えなければなりません。
- 自分にとって、必要最小限の服って何枚?
- 今、家にハンガーは何本ある?
- ハンガーのデザインや色が揃っていることは、自分にとって大事?
- そもそも、なぜハンガーが必要なのか?
- タンスに畳んで収納するという方法でもいいのでは?
つまり、必要最小限を把握するとは、モノごとに、次のような自問自答を繰り返す作業です。
- なんのために使うのか?
- いくつ持っているのか?
- 必要最小限とはどのくらいか?
- 大切なこだわり条件はないか?
- 代わりになる手段はあるか?
この考えるという行為を、私はこう定義しています。
考える=現状把握 → 自分への問いかけ → 答えを出す
このプロセスを効率よく進めるには、
やっぱり「ノートを使って書き出す」のが一番なんです。
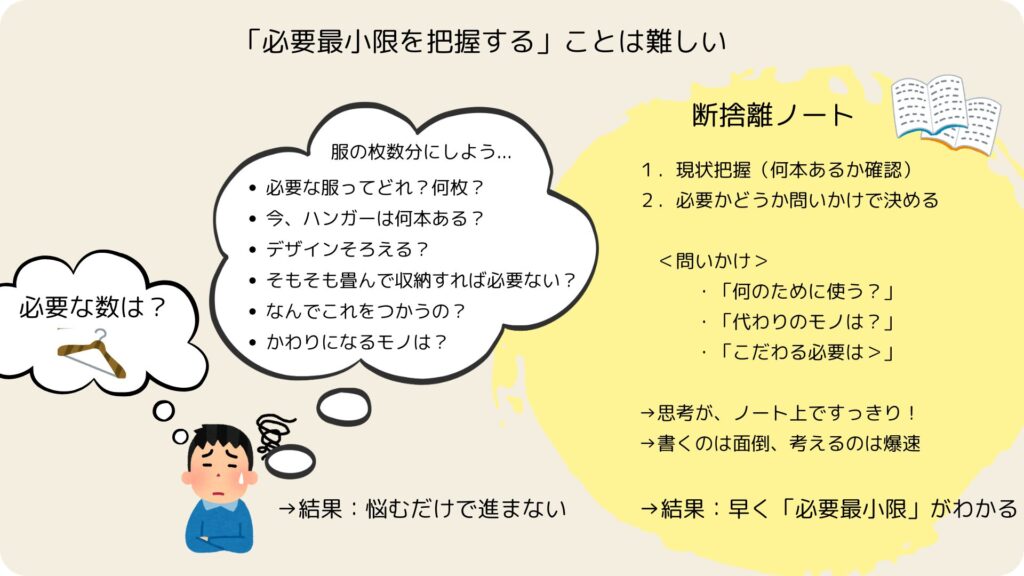
※断捨離ノートの具体的な書き方は、別記事にまとめています。
※「まとめ」の最後に掲載しております。
必要か大切か、答えはあなたの中にいる
そのモノが「必要」か「大切」か―――
その答えは、あなたの中にしかありません。
例えば、私にとって、コップは1つあれば十分。
でもあなたにとっては、
「いろんなデザインのコップを集めるのが楽しい」
「お気に入りのコップが癒しになっている」
そんな存在かもしれません。
であれば、そのコップは「必要なモノ」ではなく、「自分にとって大切なモノ」。
つまり、「これだけ残せばいい!」という共通の正解リストは存在しないのです。
本当に心地いい暮らしは、
自分が選び、自分で納得して残したモノたちに囲まれている状態。
勝手に班分けされたグループより、
昼休みに自然と集まった友達との時間のほうが、居心地がいいですよね。
モノも同じです。
「自分が本当に選んだメンバーかどうか」が、居心地を左右する。
だからこそ、必要か大切かを自分で考えることが欠かせません。
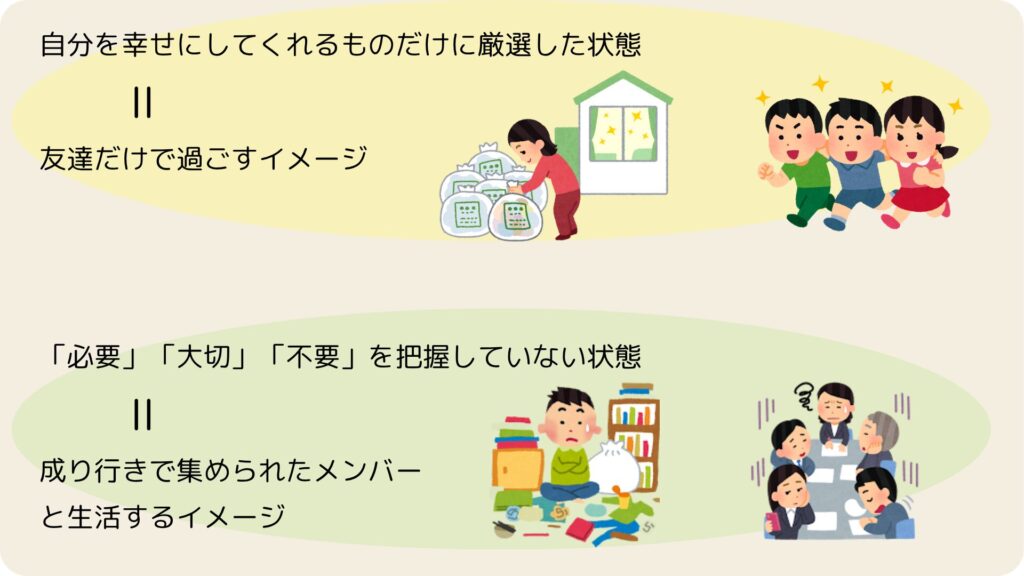
モノを見ているだけでは、必要か大切か、見分けることはできない
自分にとって何が必要なのか、何が大切なのか。
その答えを出すには──
「考えること」が欠かせません。
そしてその“考える”を助けてくれるのが、断捨離ノート。
モノを手に取りながら、頭の中だけで答えを出せるほど簡単ではありません。
「自分にとっての、必要最小限とは?」
この問いに向き合うための断捨離ノートの書き方は、次回の記事で紹介します。
書籍紹介:生きづらい人のためのミニマル戦略
今回の断捨離を深めるきっかけになったのが、こちらの本です。
生きづらい人のためのミニマル戦略:「考える力」が身につく!ものを手放す4ステップ
この本には、この記事で紹介したような内容──
- 「どこに・何が・いくつあるかを把握する暮らし」を目指す考え方
- 「断捨離ノート」の具体的な書き方や活用方法
が、わかりやすくまとまっています。
ノートに書いて考えることで、たしかに時間はかかりました。
でも今は、自分で納得して残したモノたちに囲まれて暮らしています。
その結果──
捨てて後悔したモノは、ひとつもありませんでした。
なぜなら、どのモノも「自分で選び、納得して残したメンバー」だから。
この本との出会いが、断捨離を“作業”から“対話”に変えてくれた気がします。
Kindle Unlimitedで無料配信中です。
Kindle Unlimitedは初回登録で30日間無料!
>>Kindle Unlimitedのリンクに飛びますまとめ:断捨離が進まない人は目標をもつのがおすすめ
この記事では、
断捨離が進まない…。
モノを捨てたのに、思ったほど満足感がない…。
そんな方に向けて、1つの断捨離の目標、考え方を紹介しました。
それは、
「自分を本当に幸せにしてくれるモノたち」だけに囲まれた、自分らしいミニマリストを目指す
という目標です。
この目標の中では、「幸せにしてくれるモノ」を2種類に分けて考えます。
●必要なモノ
・与えてくれる幸せ:便利さ
・対応:最小限に減らす
●大切なモノ
・与えてくれる幸せ:自信・癒し・愛情・自己肯定感などなど…
・対応:最大限に感じる
この“必要最小限”を見極めるには、「考える」ことが欠かせません。
そして、考えるために役立つのが断捨離ノートです。
ノートに書くことで、モノとじっくり向き合い、
「これは必要?大切?」と、頭の中を整理することができます。
今回紹介した書籍はこちら:
『生きづらい人のためのミニマル戦略』
考える力を使って、自分らしくモノを手放す方法が詰まっています。
断捨離ノートの具体的な書き方について
この記事では「目標と考え方」を紹介しましたが、
断捨離ノートの具体的な書き方については、こちらの記事でしょうかいしています
余談:最近断捨離を頑張っている妻
うちの妻は、もともと紙袋を捨てられないタイプでした。
でも昨日、
「本当にかわいい」と思える紙袋だけを残して、あとは捨てるという整理をしていたんです。
それを見て、正直、感動しました。
この記事では「断捨離が進まないのは目標がないから」と書きましたが、
それだけじゃなく、性格のやさしさもあるのかもしれません。
モノに感情移入してしまう。
捨てられない。
でも、それは「優しい証拠」なんだと思います。
逆に、ポイポイ捨てられる自分は、ちょっとドライなのかな?と考えさせられました。
優しい性格なりに、悩んで、迷って、選んでいる。
そんな姿から、すごく元気をもらいました。
すっきりした暮らしを意識してくれて、ありがとう。
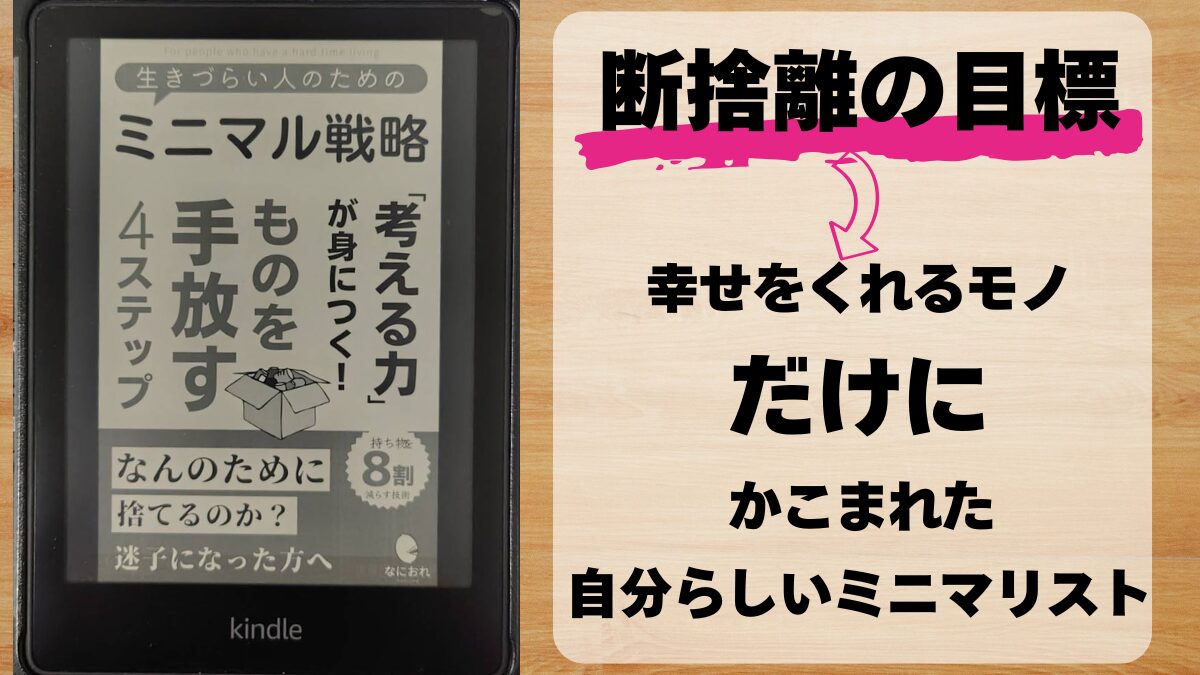
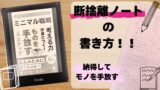

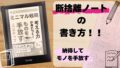
コメント